アプリケーションセキュリティおよび脆弱性管理チーム向けに、本ガイドでは自動化されたSBOMを包括的な脆弱性インテリジェンス(VI)と統合し、信頼性の高いソフトウェアインベントリを確立してゼロデイ対応をスピーディーに行うための方法を詳しく説明します。
*本記事は、弊社マキナレコードが提携する米Flashpoint社のブログ記事(2025年10月31日付)を翻訳したものです。
求められていることは明確です:ソフトウェア部品表(SBOM)の導入は、サプライチェーンの透明性を確保する上で必須となっています。しかし、透明性そのものがセキュリティを保証するわけではありません。実用的かつ包括的な脆弱性インテリジェンス(VI)の継続的なフィードがなければSBOMは単なるソフトウェアのリストにしかならず、コンプライアンス要件を満たすことはできるとしても、SBOMが静的な状態ではプロアクティブなセキュリティプログラムにもたらされる価値はほとんどなくなってしまうのです。
SBOMの真のセキュリティ上の価値は、危機が発生した際の迅速性と正確性にあります。SBOMシリーズ第2回となる今回焦点を当てるのは、SBOMの運用化についてです。組織はどうすればリアルタイムの脆弱性インテリジェンス(VI)をセキュリティワークフローに統合し、SBOMを動的な防御資産へと変えることができるのでしょうか?本記事では、SBOMをセキュリティチームの貴重な時間とコストを節約しつつ、リスクを劇的に低減させるツールへと進化させる方法について解説します。
※SBOMシリーズ第1回目の記事はこちら:「SBOM入門編:サイバーセキュリティに不可欠な透明性」
SBOMの忠実性を自動で確保
SBOMの品質は、デプロイされたコードへの忠実度によって決まります。したがって、SBOMは記述対象のソフトウェアを完全に反映した、検証済みのものでなければなりません。これを実現するため、組織はビルドプロセスに自動化を導入する必要があります。
重要なルール:CI/CDに自動化を組み込む
人的ミスや手順上の誤りの発生確率を減らすため、このプロセスは自動化され、ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)に直接組み込まれる必要があります。
- CI/CD統合:継続的インテグレーション/継続的デプロイメント(CI/CD)パイプラインのイミュータブルなアーティファクトとしてSBOMを生成することで、出荷されるコードがSBOMに過不足なく反映される仕組みを確立できます。
- ゼロトラストの原則に従う:自動化はゼロトラストの原則に沿って行います。開発者が提示している内容を信頼するのではなく、最終リリースパッケージの内容を検証するようにしましょう。
自動化プロセスを支援し運用上の価値を実現するため、読みやすく広範にサポートされている標準と統合ツールを使用してください。その一般的な選択肢としては、以下のようなものがあります:
- SPDXおよびCycloneDX:SBOMは、オープンで構造化された形式で記述される必要があります。SPDXかCycloneDXのいずれかを使用することで、手動で作業せずともセキュリティプラットフォームがデータを即座に取り込み、処理してくれるようになります。
- 統合ツール:ビルド環境内で確実に動作してくれる、定評のあるツールを活用しましょう。SyftやTernのようなオープンソースのジェネレーター、あるいはMaven、Gradle、GitHub Actionsなどの統合ビルドツールは、直接依存関係と重要な推移的依存関係をすべて捕捉できるような設定にすることが可能です。こうした依存関係は表面化していないことが多いものの、最も大きなリスクをもたらす存在です。
SBOMデータと脆弱性インテリジェンス(VI)の関連付け
正確なSBOMの生成には、複数のステップとプロセスが伴います。しかし、真のセキュリティ投資対効果はその後のステップ、つまりそのデータを意図的に消費し活用する段階で達成されます。
SBOMの価値を引き出すためには、外部の脆弱性情報および脅威インテリジェンスフィードとの関連付けが不可欠です。セキュリティチームが認識しているか否かにかかわらず、導入済みのソフトウェアは絶えず変化しています。依存関係は変動し、脆弱性が公開され、その後パッチが適用され、開発者は新たなパッケージを導入しているのです。この継続的な変動により、ほとんどのSBOMは急速に「古く」なり、実質的に無効となっていきます。これはSBOMを静的なチェックリストとして扱うことの誤りを浮き彫りにする一方で、継続的に監視される動的で「生きた」部品目録として捉える必要性を示しています。
この推移を検知し、脆弱性への対応がなされるまでの期間を最短にするための唯一の方法が、脅威ランドスケープとSBOMとの常時照合を可能にする脆弱性インテリジェンス(VI)を継続的に取得する、というものです。
- Log4Shellの教訓:ゼロデイ脆弱性「Log4Shell」が明るみになった際、SBOMを保有していた多くの組織でさえ、真に脆弱な領域を特定できませんでした。なぜでしょうか?それは、脆弱性マッピングが不十分だったためです。こうした組織は例えば、実際には「バージョン1.1」を運用しているのに「バージョン1.0」と記載されたSBOMを参照したり、具体的にどの製品が当該コンポーネントを使用しているのかに関する文脈を欠いた公開フィードに依存したりしていました。忠実度の低いSBOMにより防御が適切になされなかったことで、脆弱性の背景情報を伝えるインテリジェンスが欠如しているとSBOMは効果を発揮しなくなるという事実が浮き彫りになりました。
- 公開フィードを超えた対策:CVEやNVDなどの公開情報源と自組織のコンポーネントを単に照合するだけでは不十分です。これらの情報源には、高リスクの優先順位付けに必要な文脈、エクスプロイトの成熟度データ、独自のインテリジェンスといったものが欠けている場合が多々あります。例えば、一般に出回っているエクスプロイト(PoC)は存在するか、脅威アクターによって実際に悪用されているか、ダークウェブのフォーラムで議論の対象になっているか、といった重要な背景情報が含まれていない可能性が高いのです。
SBOMインテリジェンスの統合によるリスク低減の加速化
最後のステップは、データサイロの解消です。ここで投資の成果が現れ、プロアクティブな防御態勢の実現を叶えることができます。
- 脆弱性管理の改善:脆弱性管理チームは常にノイズとの戦いを強いられています。SBOMを脆弱性インテリジェンスプラットフォームと連携させることで、実際に使用中のコンポーネントには影響しないリスクを即座に除外できるようになります。
- インシデント対応(IR)のスピードアップ:ゼロデイ脆弱性のシナリオでは1分1秒が重要になりますが、統合されたSBOMシステムにおいては、手動だと数日かかるコンポーネントの追跡作業を即時のクエリ1つで行うことが可能なため、IRを迅速に実施することができます。各ステークホルダーに脆弱なバージョンの検索を依頼するという手間を省くことができ、代わりにSBOMが当該バージョンを実行している追跡対象資産すべてについて、即時レポートを生成してくれます。これにより修復までの時間(TTR)が劇的に短縮されます。
- 継続的なリスク態勢:SBOMデータを脅威インテリジェンスフィードと連携させることで、インシデント発生時に限らず、リスクへの露出状況を常時評価することができます。これにより、リスクの高いコンポーネントやメンテナンスされていないコンポーネント、レガシーコンポーネントを特定する能力、またプロアクティブにその除去について検討する能力が得られることとなり、「シフトレフト」のアプローチが実現します。
Flashpointの脆弱性インテリジェンス:SBOMデータを実際の対応に繋げるのためのエンジン
SBOMは、現代のサイバーセキュリティにおいて最も重要なインベントリリストです。しかし、詳細かつ実用的な脅威インテリジェンスとアクティブに統合されて関連付けが行われるまでは、単なる潜在的なエネルギーに過ぎません。目標とすべきは、単なるコンプライアンスのチェックボックスで終わらせるのではなく、SBOMデータがセキュリティスタックの動的な一部となり、迅速なインシデント対応・インテリジェンス主導の優先順位付け・実証可能なリスク低減を実現する状態を達成することです。
Flashpointが提供する高品質な脆弱性インテリジェンスが、重大な脅威へのタイムリーな対応をどう支援するのかについては、デモのリクエストをお送りください。
※日本でのFlashpointに関するお問い合わせは、弊社マキナレコードにて承っております。
また、マキナレコードではFlashpointの運用をお客様に代わって行う「マネージドインテリジェンスサービス(MIS)」も提供しております。






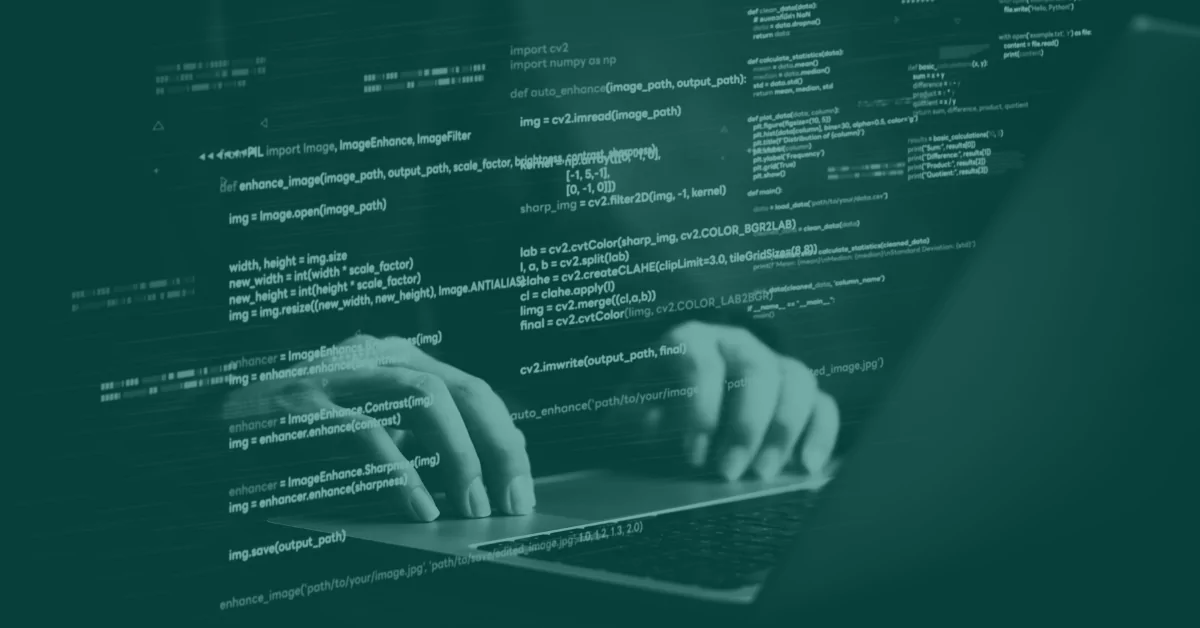












とは?.jpg)